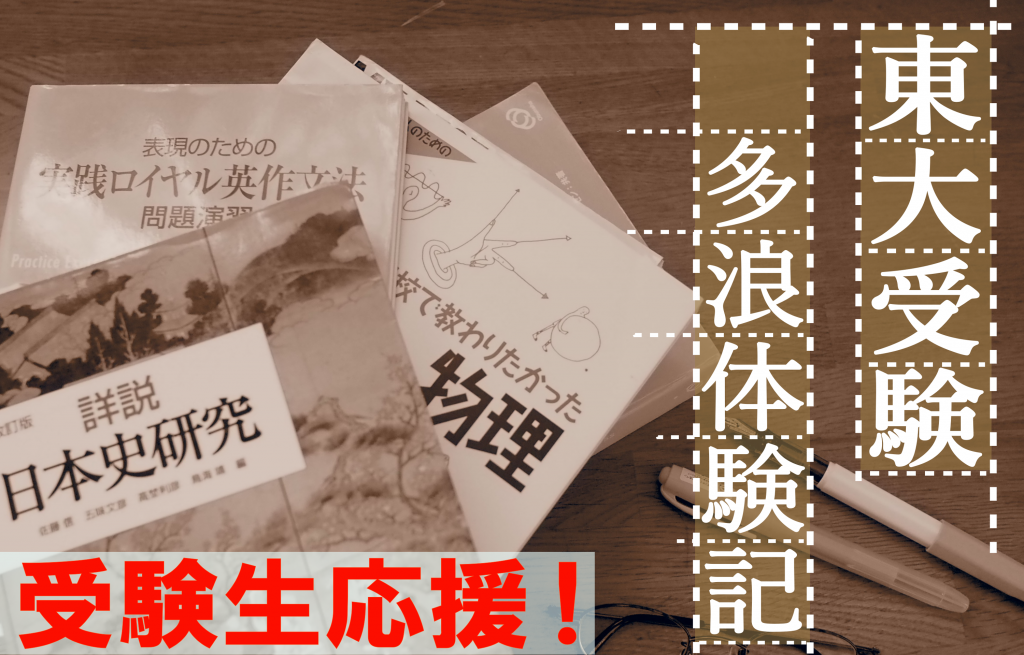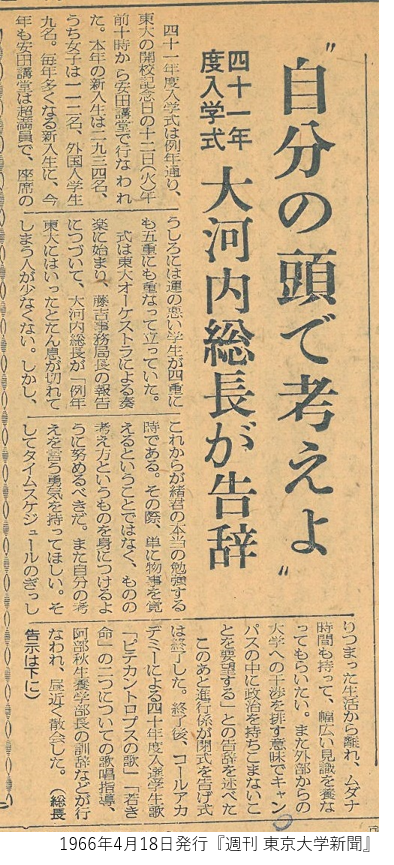受験生の皆さん。一日目の試験はどうだっただろうか。 東大生と受験について話すと、「一日目うまくいって調子に乗りすぎた。二日目もっと気を引き締めるべきだった」だとか、「一日目はうまくいかなかったが切り替えて頑張れたのが良かった」といった内容のことを言う人がよくいる。(参考:東大生に聞いた「受験当日にして良かったこと/しなければ良かったこと」)
うまくいった人もそうでなかった人も、気を引き締めなおして二日目の試験に臨もう。 今日は、二日目の科目について、東大生から受験当日の感想を聞いた。(学年は2年前の調査当時のもの)
![01_honban]()
【理科・地歴】
・模試で解答欄を間違えることがよくあったので、問題番号と行数を先に書いて「解答用紙」を作ってから解き始めた。(文系)
・世界史の大論述の下線を引き忘れたことに最後に気が付けてよかった。(文系)
・一問一答形式のものから埋めた。(文系)
・いつも世界史を早く済ませて日本史を解いていたが、本番では世界史に時間がかかり過ぎて、焦りながら日本史を解いた。途中で諦めるのも大切。(文系)
・大問1のロシアは無理だったので、取りあえずずっと中東と絡めて書いた。指定語句は使えるものだけ使って、あとはかなり雑に使った。(文系)
・とにかく書いた。世界史の大論述の出題範囲がとても苦手で、かつ暗記していなかったところだったので記憶の断片をひたすら寄せ集めていた。(文系)
・取りあえず「2」とか「1/2」とか書いた物理の穴埋めで勘が当たった。化学では大問の後ろの方にある簡単な問題や前とつながりのない問題を見逃さないことが大切。(理系)
・化学で一番得意だった構造決定と物理で出ると思っていた熱力学が出なくて焦った。(理系)
・近年は化学の問題数がとても多いことを念頭に置いておらず、化学に時間を取り過ぎて物理の時間が足りなかった。(理系)
・予想以上に物理が解けてもう少し時間をかけたかったけれど、予定時間を守って化学に行った。(理系)
・生物の考察問題を熟考の末に解くことができ非常にうれしかったので、リラックスできた。(理系)
・化学の大問3が難しいと感じて、第1問と第2問に全力を注いだ。(理系) ・解答用紙を間違えないように注意した。(理系)
・自信のない方を取りあえずできるところだけやって、あとは得意な方をじっくり考えることにした。(理系)
・好きな生物から解いてテンションを上げた。(理系)
・問題量がとても多かったので、できる問題から解き、分からなければ早々に見切りをつけた。(理系)
・理科はいつも時間がなかったので、とにかく分かる問題から解くようにした。(理系)
・傾向が変わったときは自分だけでなく周りもできないと考え落ち着くと良い。(理系)
・化学の問題料が多すぎて物理に時間が割けず点を取り切れなかった。(理系)
・残り20秒で当てずっぽうで書いた答えが当たったので、最後まで諦めないほうが良い。(理系)
・理科は計算をするよりも方針だけまとめて、なるべく多くの問題に答えた。(理系)
・理科の時間配分がうまく行かなかったが、そういうものだと思って割り切っていた。(理系)
・化学で大問3の有機の問題に40分ほどかけてしまい他の時間にかける時間が減った。(理系)
・新傾向だったが、皆もできないと考え落ち着いていた。(理系)
【英語】
・自由英作文は想像することを楽しむというスタンスで臨んだので、ストレスなく解けた。(文系)
・英作文でキーになりそうな犬もちゃんと盛り込めた。(文系)
・直前にひたすら糖分を摂取した。(文系)
・時間が足りなかった。英作文でもう少し妥協しても良かった。(理系)
・焦りすぎて1回目ではリスニングの冒頭が聴こえなかった。(理系)
・まず最初に英作文の問題で大喜利として渾身のギャグを放とうとしたが、時間をかけ過ぎて読解が解き切れなかった。(理系)
・時間がないと思い、リスニングは1回しか聴かず、得意な英作文に充てた。(理系)
・英語は練習の時から時間内に解き切るのが難しかったので、確実に得点できる部分を探して解いた。(理系)
・英作文では他の大問の文章を見ていると発想が浮かぶことがあった。リスニングに入るとき、大問の途中だったからそっちも気になりあまり集中できなかった。(理系)
・分からなくても時間配分を死守。(理系)
・リスニングまでにやろうと思っていた英作文などを全部解けていたので、余裕を持ってリスニング、その後の長文に臨めた。(理系) ・リスニングの選択肢を事前に読み始めていたので、落ち着いてできた。(理系)
・問題文の意味がわからない問題があったので読み飛ばした。(理系)
・何より時間配分が大切だったので、いつも通り落ち着いてやるよう心掛けた。周りの人がページをめくる音には少し焦った。(理系) ・疲れとこれで終わるという安心感からか、リスニング中に眠気に襲われた。(理系)
・本番にして初めてリスニングを聴きながら和訳も考えるという暴挙に出たら案の定駄目だった。(理系)
・長文が本当に何を言っているか分からなかったが、早めに切り捨てたのは正解だった。(理系)
・大教室で受験する場合はリスニングの聴こえ方に戸惑わないよう、イヤホンやヘッドホンを使わない練習もしたほうが良い。(理系)
・英語までの科目の感触から英語で50点程度取れれば受かると思っていたので、全て解けなくても良いから焦らず、一問一問確実に解いた。(理系)
この記事は2015年2月の記事の再掲です。
東大生に聞いた受験当日の感想〈理科地歴・英語編〉は東大新聞オンラインで公開された投稿です。