働き方改革が叫ばれて久しい。2016年、安倍政権が「働き方改革実現会議」を発足させて以降、残業の削減や、育休制度の拡充といった施策がその旗印のもと推進されてきた。
社会全体で働き方を見直す動きが出てきたことは、これから社会に出る若者にとっても明るいニュースなのだろう。しかし、私たち理系学生はこれまで通り、いやこれまで以上に漠然とした不安を抱いている。
「有名な大学に進学し、大手企業に行けば大丈夫」という神話は崩壊し、かつて「末は博士か大臣か」とまで言われた博士は稼ぎ口に困る。
“過労死”、”高学歴ワーキングプア”、”ポスドク問題”、etc.
そんなカードがひそむジジ抜きのような時代を生きる私たちは、どのような働き方を目指すべきなのだろうか?
今回は、そんな疑問と鬱憤をぶつけるべく、『明日クビになっても大丈夫!』の著者であり、webライターとして活躍するヨッピーさんと、『先生、それって「量子」の仕業ですか?』の著者であり、いろんな分野の研究に携わる東北大学の大関真之先生にお越しいただいた。2人の出会いはある対談記事。量子力学を噛み砕いて解説する大関先生が語る内容を、ヨッピーさんの発信力でバズらせたのだ。この2人が醸し出す普通の人とは違う面白さも気になるところだ。聞き手は、現役大学院生の須田英太郎(文化人類学専攻)と、久野美菜子(学際情報学専攻)の2人。須田、久野(筆者)ともにいわゆる”就活”の波に乗り切れず、大学院を休学中だ。
*この記事は、研究の未来をデザインするメディア「Lab-On」からの転載です。
研究者とフリーランサーに聞く、稼ぐために必要なこと【ヨッピー ✕ 大関先生対談】
研究者とフリーランサー どうやったら食べていけるの?
![]()
![]()
今日は研究者とライターという、ちょっぴり不安定そうなご職業ながら、ばりばり稼いでいらっしゃいそうな(?)お二人に、「若者はどうすれば食べていけるのか」聞いてみたいと思います。まずは、お二人が今の仕事に至るまでのことを簡単に教えてください。
![]() いまの僕の原点は、博士に進んだ時に*学振が取れなかったことにありますね。学振落ちた当時はすごく悔しかったんです。なんとなく研究者として落選的な烙印を押されたような気がしました。「学振もらわなくても食っていけるように自分で稼いでやる!(笑)」と思って予備校講師になった結果、色々な発表技術が身について、結果としてある程度の人気が出て飯が食えるようになりました。
いまの僕の原点は、博士に進んだ時に*学振が取れなかったことにありますね。学振落ちた当時はすごく悔しかったんです。なんとなく研究者として落選的な烙印を押されたような気がしました。「学振もらわなくても食っていけるように自分で稼いでやる!(笑)」と思って予備校講師になった結果、色々な発表技術が身について、結果としてある程度の人気が出て飯が食えるようになりました。
そこで気づいたのは、学振落ちただけあってそりゃあ頭がいい人にはかなわないかもしれないけど、別のプラスアルファがあれば食っていけるということ。僕の場合は話術もといプレゼンテーション技術でしたが、研究のことを上手く喋れるおかげで、結果的に研究者として上手くやっていけてる。つまり様々な能力を合わせた総合力で今に繋がっているんだと思います。
*学振:学振特別研究員の制度の略で、優れた若手研究者が研究に専念できるように、生活費及び研究費の援助を行う制度。「学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資する」という目的のもと、昭和60年度から制度がスタートした。
学振に合格した博士学生が語る面接や申請で気をつけるべきポイントとは!?
![]() 僕ももともと、いわゆる大企業で働いてたけど辞めてライターになったんですよね。なろうと思ってなったわけじゃなくて、気づいたらライターになってた、みたいな感じだから親も「あんたこれからどうすんの」ってブツブツ言ってたし周りも食べていけるのか心配してたみたいだけど、辞めたら辞めたでそんな大変じゃなかったんですよね。ライターって楽しいしお金もらえるし最高やんけ、って。文章書くのは好きで元々やってたし。
僕ももともと、いわゆる大企業で働いてたけど辞めてライターになったんですよね。なろうと思ってなったわけじゃなくて、気づいたらライターになってた、みたいな感じだから親も「あんたこれからどうすんの」ってブツブツ言ってたし周りも食べていけるのか心配してたみたいだけど、辞めたら辞めたでそんな大変じゃなかったんですよね。ライターって楽しいしお金もらえるし最高やんけ、って。文章書くのは好きで元々やってたし。
![]() 副業ならまだしも、フリーランスでちゃんと食べていくのは難しそうな印象があります。
副業ならまだしも、フリーランスでちゃんと食べていくのは難しそうな印象があります。
![]() サラリーマンとして年収をあげるのにやらなきゃいけない労力と比べれば、フリーランスが月収上げるのって簡単ですよ。サラリーマンは上司の言うこと聞いて、媚びへつらって残業して、それが認められてやっと昇給するのに対して、フリーランスは口先三寸で「もうちょっとちょうだ~~~い!」ってゴネるだけで上がったりします。
サラリーマンとして年収をあげるのにやらなきゃいけない労力と比べれば、フリーランスが月収上げるのって簡単ですよ。サラリーマンは上司の言うこと聞いて、媚びへつらって残業して、それが認められてやっと昇給するのに対して、フリーランスは口先三寸で「もうちょっとちょうだ~~~い!」ってゴネるだけで上がったりします。
![]() お二人の話を聞くと気が楽になる一方で、生き残ってるからこそ発言できるというか、生存バイアスがかかってるのではないかと思ってしまいます。
お二人の話を聞くと気が楽になる一方で、生き残ってるからこそ発言できるというか、生存バイアスがかかってるのではないかと思ってしまいます。
![]() それは確かにあるかもしれないけど、例えば東大生の場合だったら、東大出てチャレンジした結果の失敗だったら評価してくれる人はいるはず。単に就職が嫌でぷらぷらしてるわけではないし、多少の失敗はいいんじゃないのと。
それは確かにあるかもしれないけど、例えば東大生の場合だったら、東大出てチャレンジした結果の失敗だったら評価してくれる人はいるはず。単に就職が嫌でぷらぷらしてるわけではないし、多少の失敗はいいんじゃないのと。
![]() そういったチャレンジが難しいのは、誰かに評価されることにばかり慣れていて、評価の基準がわからない場所に飛び込むのが難しいからな気がします。
そういったチャレンジが難しいのは、誰かに評価されることにばかり慣れていて、評価の基準がわからない場所に飛び込むのが難しいからな気がします。
![]() 例えば大学生は受験を通して偏差値なり模試の成績で評価されてきたから、目に見えるバロメーターがないと不安なんじゃないかな。自分をどう評価してほしいか、その評価軸は自分で用意する必要があるんだよね。今はブログとかSNSもあるし、見せ方を工夫すれば仕事につながる。
例えば大学生は受験を通して偏差値なり模試の成績で評価されてきたから、目に見えるバロメーターがないと不安なんじゃないかな。自分をどう評価してほしいか、その評価軸は自分で用意する必要があるんだよね。今はブログとかSNSもあるし、見せ方を工夫すれば仕事につながる。
![]() なんかで失敗してもそのストーリーを発信してればうちにおいでよって言ってくれる人はいると思いますよ。業界にもよるけどフリーランスで頑張ってた人って即戦力だし欲しがる会社いっぱいあると思う。東大生が起業して全財産を溶かしちゃったとかね、最高の失敗談ですよね。普通に新卒で面接受けに来る人より、そういう人のほうが僕も欲しいですよ。
なんかで失敗してもそのストーリーを発信してればうちにおいでよって言ってくれる人はいると思いますよ。業界にもよるけどフリーランスで頑張ってた人って即戦力だし欲しがる会社いっぱいあると思う。東大生が起業して全財産を溶かしちゃったとかね、最高の失敗談ですよね。普通に新卒で面接受けに来る人より、そういう人のほうが僕も欲しいですよ。
![]() 発信という点では、研究者は自己表現が苦手というか、業績やキャラクター性なんかを積極的にアピールする人って多くはないですよね。
発信という点では、研究者は自己表現が苦手というか、業績やキャラクター性なんかを積極的にアピールする人って多くはないですよね。
![]() 研究者の人って頭いいはずなのにあんまりアピールが上手くないですよね。
研究者の人って頭いいはずなのにあんまりアピールが上手くないですよね。
![]()
たぶんそれは、ずっと大学に所属してるからなんですよ。最終的に教授になればいいと思っているから、論文を書けば書くほど偉いというルールで戦おうとする。でも分野によって早く書けるとこもあれば、中々結果がでないとこもあるし、本当にその軸だけで勝負しようとすると難しい。
![]() 自分のほうがデキると思ってたのに、同級生に差をつけられて先に教授になられたら面白くないですもんね。
自分のほうがデキると思ってたのに、同級生に差をつけられて先に教授になられたら面白くないですもんね。
![]() でしょ。だけど他にも評価軸を持つような活動があれば、別の部分で評価されるし、最終的には研究の幅が人脈とともに広がるので良い。兼業であれば所属しているところの決まりの範囲であればお金も入るから一石二鳥。
でしょ。だけど他にも評価軸を持つような活動があれば、別の部分で評価されるし、最終的には研究の幅が人脈とともに広がるので良い。兼業であれば所属しているところの決まりの範囲であればお金も入るから一石二鳥。
![]() そうか。でも研究者の評価軸って論文以外にどんなのがあるんでしょう?
そうか。でも研究者の評価軸って論文以外にどんなのがあるんでしょう?
![]() 僕の場合は、講演会に呼ばれたり、デザインの仕事が貰えたりするのだけど、そこで大事なのは「話せること」と「置き換えられること」の二つかな、と思います。理系の人が文系の人に伝えるのも大事だし、相手が理解しやすい言葉やデザインに翻訳する必要がある。
僕の場合は、講演会に呼ばれたり、デザインの仕事が貰えたりするのだけど、そこで大事なのは「話せること」と「置き換えられること」の二つかな、と思います。理系の人が文系の人に伝えるのも大事だし、相手が理解しやすい言葉やデザインに翻訳する必要がある。
![]() 大関先生の話は、確かに素人の人でもわかりやすいですよね。それこそが翻訳の本質と言いますか。ただ研究者の中には、素人でもわかるように、って翻訳するのを恥と思ってる人もいそうですね(笑)。
大関先生の話は、確かに素人の人でもわかりやすいですよね。それこそが翻訳の本質と言いますか。ただ研究者の中には、素人でもわかるように、って翻訳するのを恥と思ってる人もいそうですね(笑)。
![]() 正しいこと、確かなことを積み重ねて真理に近づく訓練を経て、妥協をしないことが求められていますからね。でも周囲の人に自分たちがやっていることが伝わらず、理解者が減ってしまい、その分野が終わってしまうリスクを考えると、言ってみれば周りのファンを増やしたほうが得だし楽しいと思うのですよね。
正しいこと、確かなことを積み重ねて真理に近づく訓練を経て、妥協をしないことが求められていますからね。でも周囲の人に自分たちがやっていることが伝わらず、理解者が減ってしまい、その分野が終わってしまうリスクを考えると、言ってみれば周りのファンを増やしたほうが得だし楽しいと思うのですよね。
![]() ある分野ど真ん中の人だけではなく、ファンを増やすって素敵ですね。翻訳の難しさってどういうところにあるのでしょうか?
ある分野ど真ん中の人だけではなく、ファンを増やすって素敵ですね。翻訳の難しさってどういうところにあるのでしょうか?
![]() 素朴に難しいのは、共通の言葉がないこと、ですよね。だから翻訳は難しい。数式を使えばわかるといっても、その数式を表す言葉がなかなか見つからないから数式を使っているわけですから。でもそれは研究者自身が外に出て、日本語を覚えればできることです(笑)。僕も講演の度にちょこちょこ言い方を変えるんです。受けを探る。そうするとこうやって表現すればわかりやすいのだな、みんなが感じ取ることができるのだな、とわかります。同時にこの表現は言いすぎた、と家で一人ズドーーーーーンと落ち込むこともあります。この話、初めてするかも。こうやって訓練していくんですよ。
素朴に難しいのは、共通の言葉がないこと、ですよね。だから翻訳は難しい。数式を使えばわかるといっても、その数式を表す言葉がなかなか見つからないから数式を使っているわけですから。でもそれは研究者自身が外に出て、日本語を覚えればできることです(笑)。僕も講演の度にちょこちょこ言い方を変えるんです。受けを探る。そうするとこうやって表現すればわかりやすいのだな、みんなが感じ取ることができるのだな、とわかります。同時にこの表現は言いすぎた、と家で一人ズドーーーーーンと落ち込むこともあります。この話、初めてするかも。こうやって訓練していくんですよ。
![]() 本来は僕みたいなライターや新聞記者さんなんかがやるべき仕事なんでしょうけどね。でも研究者の方が自分達で全部発信するようになったら僕の仕事がなくなっちゃうな~~! おとなしくしてて下さい(笑)。
本来は僕みたいなライターや新聞記者さんなんかがやるべき仕事なんでしょうけどね。でも研究者の方が自分達で全部発信するようになったら僕の仕事がなくなっちゃうな~~! おとなしくしてて下さい(笑)。
研究者は本当にお金に困ってるのか?
![]() ところでいまって研究者がお金困ってるみたいな話凄い聞きますよね。iPS細胞研究所の山中伸弥先生が募金の募集かけてたの見てびっくりしたんですけど、世界的にも有名ですごい山中先生みたいな人が研究費に困ってるのっておかしくないですか……?「日本の科学技術大丈夫……?」ってすごい思いました。もちろんこうやって発信して協力を呼び掛ける活動自体は素晴らしいと思うんですけど……。
ところでいまって研究者がお金困ってるみたいな話凄い聞きますよね。iPS細胞研究所の山中伸弥先生が募金の募集かけてたの見てびっくりしたんですけど、世界的にも有名ですごい山中先生みたいな人が研究費に困ってるのっておかしくないですか……?「日本の科学技術大丈夫……?」ってすごい思いました。もちろんこうやって発信して協力を呼び掛ける活動自体は素晴らしいと思うんですけど……。
![]() 京都大学iPS細胞研究所HPより引用
京都大学iPS細胞研究所HPより引用
![]()
本当の意味で金が足りていないところもあります。コピー代や部屋の冷暖房代もままならないところとか。それ以上に研究資金は使用用途が限られていたり、期限があるものが多いから、ダイナミックな動きをしたい時に両手が縛られてしまっている、という状態になりがちなんですよ。あと基本的には繰越もできない。でもそういう状況は一般的に知られていない。
![]() なるほど、国から予算をもらっても好き放題使えるわけじゃないんだ。 長期的な目線でやる投資なんかには向いてないんですね。どうしたらいいんですかね?
なるほど、国から予算をもらっても好き放題使えるわけじゃないんだ。 長期的な目線でやる投資なんかには向いてないんですね。どうしたらいいんですかね?
![]() 研究者が大学に閉じこもってたら無理で、他のところに発信したり出かけたりすると、そう言った実情を知ってもらえるわけです。最近Twitter等でもそう言った情報が伝わるようになっていますよね。それで河野太郎さんが改革に向けて動いてくれたりする。ただ僕らが騒いでいるだけだと、どうしても研究者界隈で限られてしまいますよね。僕は美術館に声をかけてもらって講演をしたもことあって、やや繋がりがわけのわからない変わった研究者ですけど、これは非常にメリットがあって、これまで関わりのなかったクラスターに知ってもらえるわけです。研究を進めるために、実はお金に困ってるって言ったら「じゃあお金出してあげるから、一緒に新しいプロジェクトやろうよ」と意外なところから言ってもらえたりします。そうすると自分のところの任期あり研究員の寿命を伸ばすことにつながります。任期があっても活躍して外に出る人が多いことは良いのですが、一方で安心してじっくりと研究を進めることのできる環境づくりも重要で、そのために期限のあるお金って、それ自体は非常にありがたいものの、研究の効率化に向けた本質的な解決につながりにくいのですよね。
研究者が大学に閉じこもってたら無理で、他のところに発信したり出かけたりすると、そう言った実情を知ってもらえるわけです。最近Twitter等でもそう言った情報が伝わるようになっていますよね。それで河野太郎さんが改革に向けて動いてくれたりする。ただ僕らが騒いでいるだけだと、どうしても研究者界隈で限られてしまいますよね。僕は美術館に声をかけてもらって講演をしたもことあって、やや繋がりがわけのわからない変わった研究者ですけど、これは非常にメリットがあって、これまで関わりのなかったクラスターに知ってもらえるわけです。研究を進めるために、実はお金に困ってるって言ったら「じゃあお金出してあげるから、一緒に新しいプロジェクトやろうよ」と意外なところから言ってもらえたりします。そうすると自分のところの任期あり研究員の寿命を伸ばすことにつながります。任期があっても活躍して外に出る人が多いことは良いのですが、一方で安心してじっくりと研究を進めることのできる環境づくりも重要で、そのために期限のあるお金って、それ自体は非常にありがたいものの、研究の効率化に向けた本質的な解決につながりにくいのですよね。
![]() 確かに理系の大学の先生でも、お金を取ってくるのが上手い人と下手な人がいますよね。
確かに理系の大学の先生でも、お金を取ってくるのが上手い人と下手な人がいますよね。
![]() その差異は基本的に実績もありますが、それを正しく伝える作文力と発信力ですね。ただ一人の大学の先生に発信を押し付けもダメで、組織として外に発信する媒体が上手く使えてないのが問題で。研究の発信というと研究内容の発信と思われがちだけど、普段どういうふうに生きてるのか、どういう人間なのかというのを伝えるともっと興味を持ってもらえると思いますね。
その差異は基本的に実績もありますが、それを正しく伝える作文力と発信力ですね。ただ一人の大学の先生に発信を押し付けもダメで、組織として外に発信する媒体が上手く使えてないのが問題で。研究の発信というと研究内容の発信と思われがちだけど、普段どういうふうに生きてるのか、どういう人間なのかというのを伝えるともっと興味を持ってもらえると思いますね。
![]() その辺の発信は将棋が最近うまいなーと思ってます。あと近畿大学も。将棋はニコ生と組んで電脳戦とかやったりして、棋士の人となりにスポットライトが当たりますし。将棋界と研究界って似た部分がありますよね。どちらも変人が多いし(笑)。理系の研究者もじゅうぶんコンテンツになると思うんです。僕以前、数学者の千葉先生にお話聞いて記事にしたんですけどめちゃくちゃ面白かったですもん。
その辺の発信は将棋が最近うまいなーと思ってます。あと近畿大学も。将棋はニコ生と組んで電脳戦とかやったりして、棋士の人となりにスポットライトが当たりますし。将棋界と研究界って似た部分がありますよね。どちらも変人が多いし(笑)。理系の研究者もじゅうぶんコンテンツになると思うんです。僕以前、数学者の千葉先生にお話聞いて記事にしたんですけどめちゃくちゃ面白かったですもん。
「数学者は変人ばかり」って本当? 天才数学者・千葉逸人先生に聞いてきた
![]() うちの研究員と一緒にYouTuberデビューしようかなんて話も最近してますからね(笑)。それで好循環が生まれたら色んな研究者のYouTubeチャンネルや動画コンテンツが出来て研究界隈が広く盛り上がるんじゃないかと。応援もしやすいし、知ってもらえるチャンスが広がります。大きなことを言えば、溢れる情報の中でうまく知ってもらえないと、科学技術に予算をつける、ということに理解してもらえなくなります。
うちの研究員と一緒にYouTuberデビューしようかなんて話も最近してますからね(笑)。それで好循環が生まれたら色んな研究者のYouTubeチャンネルや動画コンテンツが出来て研究界隈が広く盛り上がるんじゃないかと。応援もしやすいし、知ってもらえるチャンスが広がります。大きなことを言えば、溢れる情報の中でうまく知ってもらえないと、科学技術に予算をつける、ということに理解してもらえなくなります。
![]() 交付金が減らされててしんどいという話はよく聞くけど、増えるのを待つ以外の作戦も何かしら打たなきゃいけないと思うんですよね。
交付金が減らされててしんどいという話はよく聞くけど、増えるのを待つ以外の作戦も何かしら打たなきゃいけないと思うんですよね。
![]() 現状予算が限られてるんだから考えなきゃいけない。お金がない!って愚痴を言っていてもしょうがない。ファンを増やして今までとは違うところからの応援をしてもらおうよ、と思います。究極的にはプロ野球みたいになれば面白いですよね。まあそれで外に出て色々出稼ぎをすることにしたわけです(笑)。
現状予算が限られてるんだから考えなきゃいけない。お金がない!って愚痴を言っていてもしょうがない。ファンを増やして今までとは違うところからの応援をしてもらおうよ、と思います。究極的にはプロ野球みたいになれば面白いですよね。まあそれで外に出て色々出稼ぎをすることにしたわけです(笑)。
![]() それでも研究者で兼業や副業してる人が少ないのはどうしてなのでしょう?
それでも研究者で兼業や副業してる人が少ないのはどうしてなのでしょう?
![]() やり方を知らないんじゃないかなぁ。
やり方を知らないんじゃないかなぁ。
![]()
え、そもそも大学の先生って兼業してもいいの?
![]() オッケーです。法人化されて僕らは公務員ではなくなったので。例えば講演を外でして、そこで謝金をもらう場合も兼業です。複数の箇所で研究活動をする場合には、最近できたのはクロスアポイントメント制度っていうのがあって、その人の働く割合を半々にするとか配分をして働くことができたりもします。
オッケーです。法人化されて僕らは公務員ではなくなったので。例えば講演を外でして、そこで謝金をもらう場合も兼業です。複数の箇所で研究活動をする場合には、最近できたのはクロスアポイントメント制度っていうのがあって、その人の働く割合を半々にするとか配分をして働くことができたりもします。
![]() 専門的な話が出来るから講演だったり、外で事業するとか会社のコンサルティングとかもありえますよね。
専門的な話が出来るから講演だったり、外で事業するとか会社のコンサルティングとかもありえますよね。
![]() たとえば量子コンピューターだとどんな事業があるんですか?
たとえば量子コンピューターだとどんな事業があるんですか?
![]() 量子コンピューターに関して言えば、実際の応用先に様々な産業から「こんなことってできますか?」という相談が舞い込んでいます。まさにコンサルティングですよね。さらに最近増えているのは、投資関係からの相談です。量子コンピュータ関係の技術が進んでいるらしいけど、実際のところどうなのか?今後のびる分野はどこなのか?などなど色々と相談が来ます。
量子コンピューターに関して言えば、実際の応用先に様々な産業から「こんなことってできますか?」という相談が舞い込んでいます。まさにコンサルティングですよね。さらに最近増えているのは、投資関係からの相談です。量子コンピュータ関係の技術が進んでいるらしいけど、実際のところどうなのか?今後のびる分野はどこなのか?などなど色々と相談が来ます。
![]() あーなるほど! 投資家の人はお金を握ってても、投資先がほんとに技術もってるかとかわからないですもんね。そういう時に大学の先生「ここに投資しようと思ってるんだけど、大丈夫かな?」って知恵貸してもらえるなら、優秀な頭脳の良い使い方ですよね。
あーなるほど! 投資家の人はお金を握ってても、投資先がほんとに技術もってるかとかわからないですもんね。そういう時に大学の先生「ここに投資しようと思ってるんだけど、大丈夫かな?」って知恵貸してもらえるなら、優秀な頭脳の良い使い方ですよね。
![]() 企業と大学って、現状すごく離れてるんですよ。清貧になれという先生もいるけど、貧だとどうしようもない。企業の人と関わることで、何が求められるか、こういうことが一緒にやることで出来るという可能性がわかったりする。そうしたら次はどういう研究しようかなという考えの幅がもがります。
企業と大学って、現状すごく離れてるんですよ。清貧になれという先生もいるけど、貧だとどうしようもない。企業の人と関わることで、何が求められるか、こういうことが一緒にやることで出来るという可能性がわかったりする。そうしたら次はどういう研究しようかなという考えの幅がもがります。
![]() フリーの研究者と言うのは今後出てきたりしないのでしょうか?大学の研究者向けのアウトソーシングとかあれば、ポストに困ってる研究者も研究人材欲しい企業も助かりそう。
フリーの研究者と言うのは今後出てきたりしないのでしょうか?大学の研究者向けのアウトソーシングとかあれば、ポストに困ってる研究者も研究人材欲しい企業も助かりそう。
![]() 出て来るんじゃないですか?個人的にはこのままだと大学はつぶれてしまうと思ってるんで。だって毎年運営交付金を削減されて、人件費も削られて。人がいないから研究も講義もできなくなってくる。フリーの研究者を認めて、大学に所属は残しながら、企業とも自由にやったらいいと思います。
出て来るんじゃないですか?個人的にはこのままだと大学はつぶれてしまうと思ってるんで。だって毎年運営交付金を削減されて、人件費も削られて。人がいないから研究も講義もできなくなってくる。フリーの研究者を認めて、大学に所属は残しながら、企業とも自由にやったらいいと思います。
大学と企業が抱える不合理さ どうすれば変えられる?
![]() ヨッピーさんのご著書『クビになっても大丈夫』の中で、上司に出す印鑑は「左に傾ける」ように言われてナンセンスだと思った、というエピソードがありました。
ヨッピーさんのご著書『クビになっても大丈夫』の中で、上司に出す印鑑は「左に傾ける」ように言われてナンセンスだと思った、というエピソードがありました。
![]() サラリーマンやってると不合理なことは色々ありましたよ。稟議書の書式が死ぬほど面倒臭いとか決済にやたらと時間がかかるとか。「お世話になります」って必ずつけなきゃいけないビジネスメールとかもやめちゃえばいいのにね。
サラリーマンやってると不合理なことは色々ありましたよ。稟議書の書式が死ぬほど面倒臭いとか決済にやたらと時間がかかるとか。「お世話になります」って必ずつけなきゃいけないビジネスメールとかもやめちゃえばいいのにね。
![]() (苦笑)。同じように理に合わないことが大学内でもありそうな気がします。神エクセル問題とか。そういうのがなかなか変わらないのって、なぜなのでしょうか?
(苦笑)。同じように理に合わないことが大学内でもありそうな気がします。神エクセル問題とか。そういうのがなかなか変わらないのって、なぜなのでしょうか?
![]() 多くの会社で聞くんですが、2-3年単位で部署を移動させて人をぐるぐる回して、どんな仕事もできるようにさせますよね。だからひどい部署行っても、3年我慢すれば別の部署に行ける。すると改善するモチベーションてわかなくなりますよね。同じように、大学の先生達にも大学を運営するための委員会がたーくさんあって、任期が1-2年なんですよね。まあ数年我慢すればいいと思うと、環境やルールが不合理でも頑張って改善しようと思わなくなる。
多くの会社で聞くんですが、2-3年単位で部署を移動させて人をぐるぐる回して、どんな仕事もできるようにさせますよね。だからひどい部署行っても、3年我慢すれば別の部署に行ける。すると改善するモチベーションてわかなくなりますよね。同じように、大学の先生達にも大学を運営するための委員会がたーくさんあって、任期が1-2年なんですよね。まあ数年我慢すればいいと思うと、環境やルールが不合理でも頑張って改善しようと思わなくなる。
![]()
教授会のようなものですか? 決めることが多くて大変だと、周りの先生方からよく聞きます。
![]() 大学によりけりだと思いますが、うちの研究科は教授会は3カ月に1回で頑張って終わらせます。研究第一主義という理念を持った大学なので(笑)。
大学によりけりだと思いますが、うちの研究科は教授会は3カ月に1回で頑張って終わらせます。研究第一主義という理念を持った大学なので(笑)。
![]() 私が前にいたラボの先生はもっと多かったです。組織運営研究しながら学生の指導して組織も運営するってすごく大変そうですね……。
私が前にいたラボの先生はもっと多かったです。組織運営研究しながら学生の指導して組織も運営するってすごく大変そうですね……。
![]() 研究が大好きな先生ならマネジメントにも教育にも興味ないし研究だけやらしてくれって思うでしょうね。分離しちゃえばいいのでは?
研究が大好きな先生ならマネジメントにも教育にも興味ないし研究だけやらしてくれって思うでしょうね。分離しちゃえばいいのでは?
![]() 結局は人がいないから割り振れないんですよね。1人十役くらいしないと回らない。海外では研究する人、教育する人、経営する人と割と分離しているようですが。
結局は人がいないから割り振れないんですよね。1人十役くらいしないと回らない。海外では研究する人、教育する人、経営する人と割と分離しているようですが。
![]() やっぱお金がないのが問題なんですかね?
やっぱお金がないのが問題なんですかね?
![]() 金はないといえばないし、それは今に始まった話ではないから、あるといわれたらたぶんあるんですよ。使い勝手と使い方の問題だと思います。期限が短いのと使用先が限られてるから問題。成果が出てるとお金はつぎ込まれるけど、数億円もらっても一定の期間内に使い切らないといけない。そのお金を数年と言わず10年にしてもらえればできることがあるわけです。人を雇うとか。この前3年のプロジェクトを申請したんですよ。優秀な人を雇って一緒にもりたてるという内容で。そうしたら、通してやるけど1.5年ね、と言われました。申請内容わかっている?って呆れてしまいました。そんな短い時間、引っ越しして新しい仕事をやるなんて相当なハードルですよね。
金はないといえばないし、それは今に始まった話ではないから、あるといわれたらたぶんあるんですよ。使い勝手と使い方の問題だと思います。期限が短いのと使用先が限られてるから問題。成果が出てるとお金はつぎ込まれるけど、数億円もらっても一定の期間内に使い切らないといけない。そのお金を数年と言わず10年にしてもらえればできることがあるわけです。人を雇うとか。この前3年のプロジェクトを申請したんですよ。優秀な人を雇って一緒にもりたてるという内容で。そうしたら、通してやるけど1.5年ね、と言われました。申請内容わかっている?って呆れてしまいました。そんな短い時間、引っ越しして新しい仕事をやるなんて相当なハードルですよね。
![]() あーなるほど。民間でも同じようなことがありますね。僕広告の仕事やってるんですが、忙しいのって9月と12月と3月なんです。要は予算の締めで、広告費用って半期でこんだけ、年間でこんだけでとってくるから、予算をちょっと余らせておくんです。で、余った予算を使うために「9月末3月末になんかやってくれ」って依頼される。
あーなるほど。民間でも同じようなことがありますね。僕広告の仕事やってるんですが、忙しいのって9月と12月と3月なんです。要は予算の締めで、広告費用って半期でこんだけ、年間でこんだけでとってくるから、予算をちょっと余らせておくんです。で、余った予算を使うために「9月末3月末になんかやってくれ」って依頼される。
![]() 大学では、2月3月くらいに文房具とかパソコン買わないでくれという通達が来ますね。使い切っているように思われないため、という。期限が決まっていると相当計画立ててやらないと研究費を効果的には使えないですよ。そう言ったマネジメントの訓練をされた人がやっているわけでもないし、そういう人を雇うこともできないルールですし。上手く配分して制約取っ払う、さらにマネジメントができる人を雇っても良いとする。そうすれば無駄も減って闇雲に予算をとる競争も減るかもしれない。今は年度ごと予算がなくなることが必至だから、とにかく生き延びるために毎回申請書を出さないといけない。だから書類仕事で苦しむのです。研究のできる環境なんてありやしない。
大学では、2月3月くらいに文房具とかパソコン買わないでくれという通達が来ますね。使い切っているように思われないため、という。期限が決まっていると相当計画立ててやらないと研究費を効果的には使えないですよ。そう言ったマネジメントの訓練をされた人がやっているわけでもないし、そういう人を雇うこともできないルールですし。上手く配分して制約取っ払う、さらにマネジメントができる人を雇っても良いとする。そうすれば無駄も減って闇雲に予算をとる競争も減るかもしれない。今は年度ごと予算がなくなることが必至だから、とにかく生き延びるために毎回申請書を出さないといけない。だから書類仕事で苦しむのです。研究のできる環境なんてありやしない。
![]() こうなると仕組みの問題であって政治家の仕事ですよね。
こうなると仕組みの問題であって政治家の仕事ですよね。
![]() 研究者を守るって言ってもね、投票数につながらないですからね。この手の話って単純にお金がないと訴えがちですけど、他の大事な国の事業はありますから、それは筋が悪いと思います。本当の意義のある改善には繋がらない。ないならないなりにちゃんといい形にするべきですからね。でもそれをうまく伝えるのは難しいですよね。
研究者を守るって言ってもね、投票数につながらないですからね。この手の話って単純にお金がないと訴えがちですけど、他の大事な国の事業はありますから、それは筋が悪いと思います。本当の意義のある改善には繋がらない。ないならないなりにちゃんといい形にするべきですからね。でもそれをうまく伝えるのは難しいですよね。
![]() だから声が届かずに仕分けられちゃう……。
だから声が届かずに仕分けられちゃう……。
![]()
たぶん政治家の多くも、大学関係者がどう困ってるかわからないんですよね。
![]() 政治家だっていやがらせしてるわけじゃないし、現に国は無理のない範囲で、多額なお金を投入しているわけで。僕らはその範囲ででもちゃんとやらないと。ただいますぐにできることはファンを増やして、外からの応援で、できないことをできるようにする。いまの研究をちゃんとやることです。
政治家だっていやがらせしてるわけじゃないし、現に国は無理のない範囲で、多額なお金を投入しているわけで。僕らはその範囲ででもちゃんとやらないと。ただいますぐにできることはファンを増やして、外からの応援で、できないことをできるようにする。いまの研究をちゃんとやることです。
![]() これまでの議論を聞いていて、研究者の発信がキーになるのかなと思いました。個人で研究の営みを発信するのに加えて、複数の研究者でコンソーシアムをつくり、研究しやすい法律や制度を求めるのも重要なのかもしれないですね。最後に、研究者になりたいと思ってる理系学生はどんな能力をつけるべきか教えてください。
これまでの議論を聞いていて、研究者の発信がキーになるのかなと思いました。個人で研究の営みを発信するのに加えて、複数の研究者でコンソーシアムをつくり、研究しやすい法律や制度を求めるのも重要なのかもしれないですね。最後に、研究者になりたいと思ってる理系学生はどんな能力をつけるべきか教えてください。
![]() デザイン力。見せ方をデザインする。やっぱかっこよくないといけない。綺麗だったり面白かったり、魅力があるようにしないと。たとえば「数学が得意です」というのはすごく重要だけど、それは研究者のベースであって、そこからさらに活躍するためには数学が得意なことを知られないとダメで。
デザイン力。見せ方をデザインする。やっぱかっこよくないといけない。綺麗だったり面白かったり、魅力があるようにしないと。たとえば「数学が得意です」というのはすごく重要だけど、それは研究者のベースであって、そこからさらに活躍するためには数学が得意なことを知られないとダメで。
![]()
研究をバズらせるtipsとかあるんでしょうか?
![]() ブログにも研究にも言えると思うんですけど、ちゃんと身近なものに翻訳することですね。「松阪牛をアレンジして美味しく食べる方法」より、「コンビニのおにぎりを美味しく食べる方法」のほうがバズるじゃないですか。千葉逸人先生がビールの泡のでき方をベルヌーイの定理で考察するみたいな事をTwitterでやっててすごいシェアされてたんですけど、やっぱりたくさんの人にとって身近にあるものに置きかえて、マーケットを広げるのがいいんじゃないですかね。たぶん。全部カンで言ってますけど。
ブログにも研究にも言えると思うんですけど、ちゃんと身近なものに翻訳することですね。「松阪牛をアレンジして美味しく食べる方法」より、「コンビニのおにぎりを美味しく食べる方法」のほうがバズるじゃないですか。千葉逸人先生がビールの泡のでき方をベルヌーイの定理で考察するみたいな事をTwitterでやっててすごいシェアされてたんですけど、やっぱりたくさんの人にとって身近にあるものに置きかえて、マーケットを広げるのがいいんじゃないですかね。たぶん。全部カンで言ってますけど。
![]()
あと、この記事を呼んでいる学生の皆さん、
![]()
将来偉くなったら仕事を下さい。
(取材・須田英太郎、久野美菜子 文・久野美菜子 )
研究者とフリーランサーに聞く、稼ぐために必要なこと【ヨッピー×大関先生対談】は東大新聞オンラインで公開された投稿です。






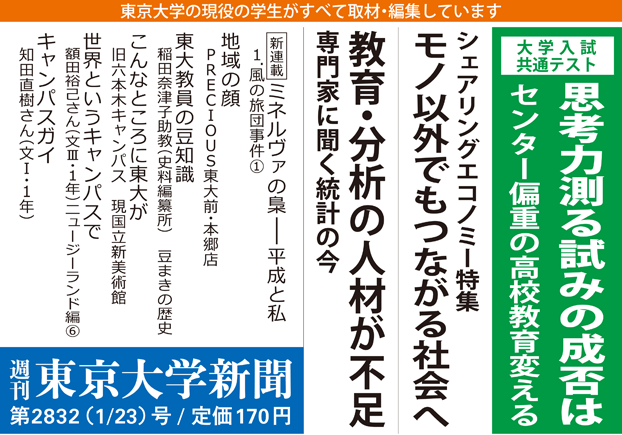












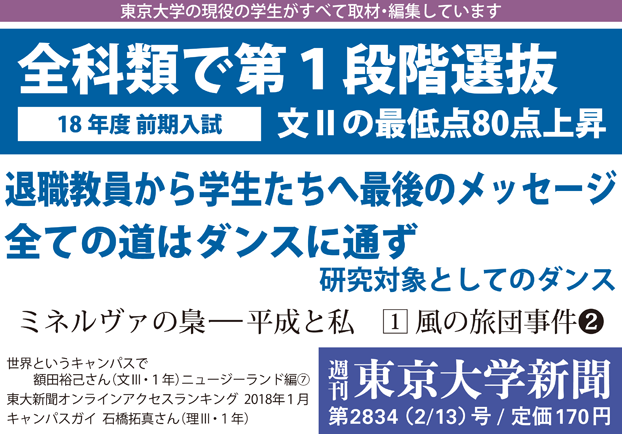


 いまの僕の原点は、博士に進んだ時に*学振
いまの僕の原点は、博士に進んだ時に*学振 僕ももともと、いわゆる大企業で働いてたけど辞めてライターになったんですよね。なろうと思ってなったわけじゃなくて、気づいたらライターになってた、みたいな感じだから親も「あんたこれからどうすんの」ってブツブツ言ってたし周りも食べていけるのか心配してたみたいだけど、辞めたら辞めたでそんな大変じゃなかったんですよね。ライターって楽しいしお金もらえるし最高やんけ、って。文章書くのは好きで元々やってたし。
僕ももともと、いわゆる大企業で働いてたけど辞めてライターになったんですよね。なろうと思ってなったわけじゃなくて、気づいたらライターになってた、みたいな感じだから親も「あんたこれからどうすんの」ってブツブツ言ってたし周りも食べていけるのか心配してたみたいだけど、辞めたら辞めたでそんな大変じゃなかったんですよね。ライターって楽しいしお金もらえるし最高やんけ、って。文章書くのは好きで元々やってたし。 そういったチャレンジが難しいのは、誰かに評価されることにばかり慣れていて、評価の基準がわからない場所に飛び込むのが難しいからな気がします。
そういったチャレンジが難しいのは、誰かに評価されることにばかり慣れていて、評価の基準がわからない場所に飛び込むのが難しいからな気がします。

