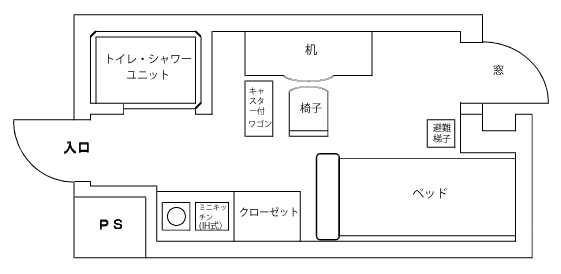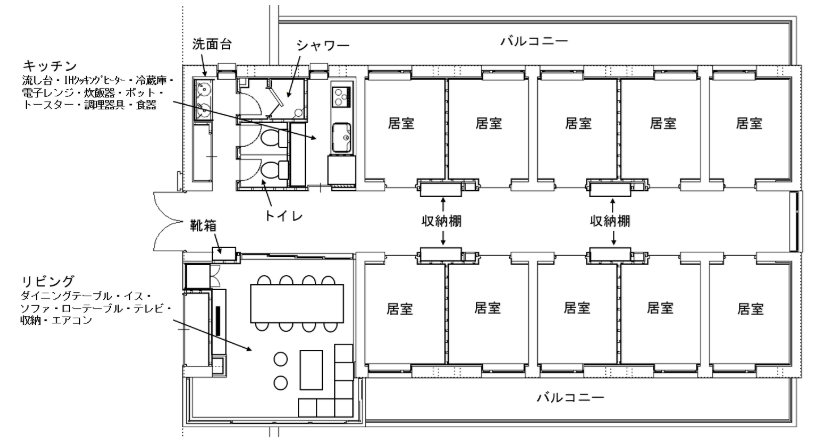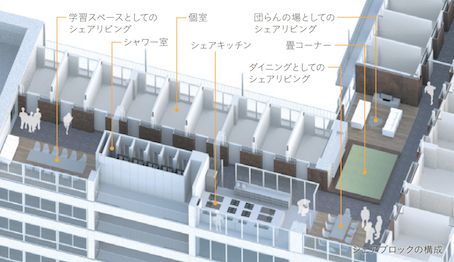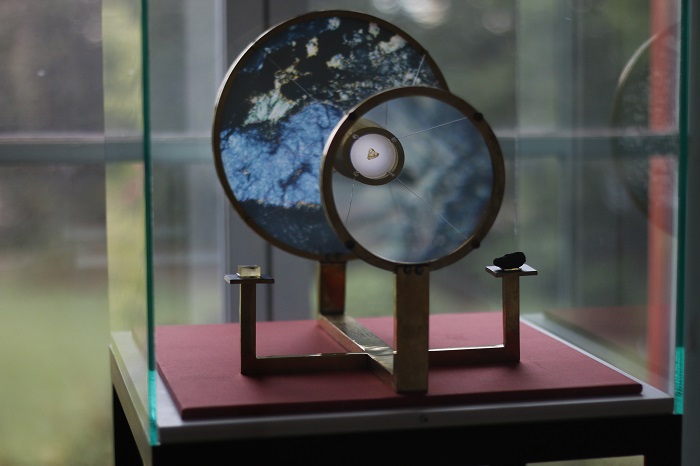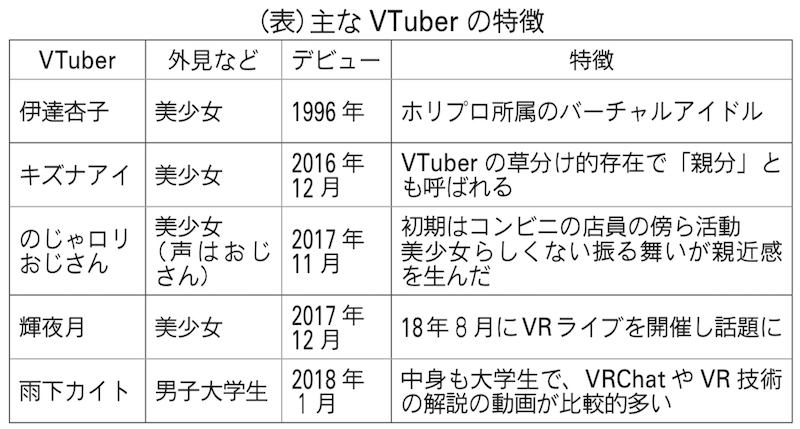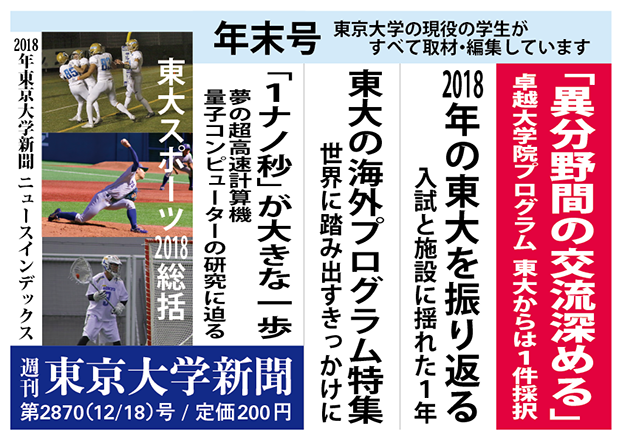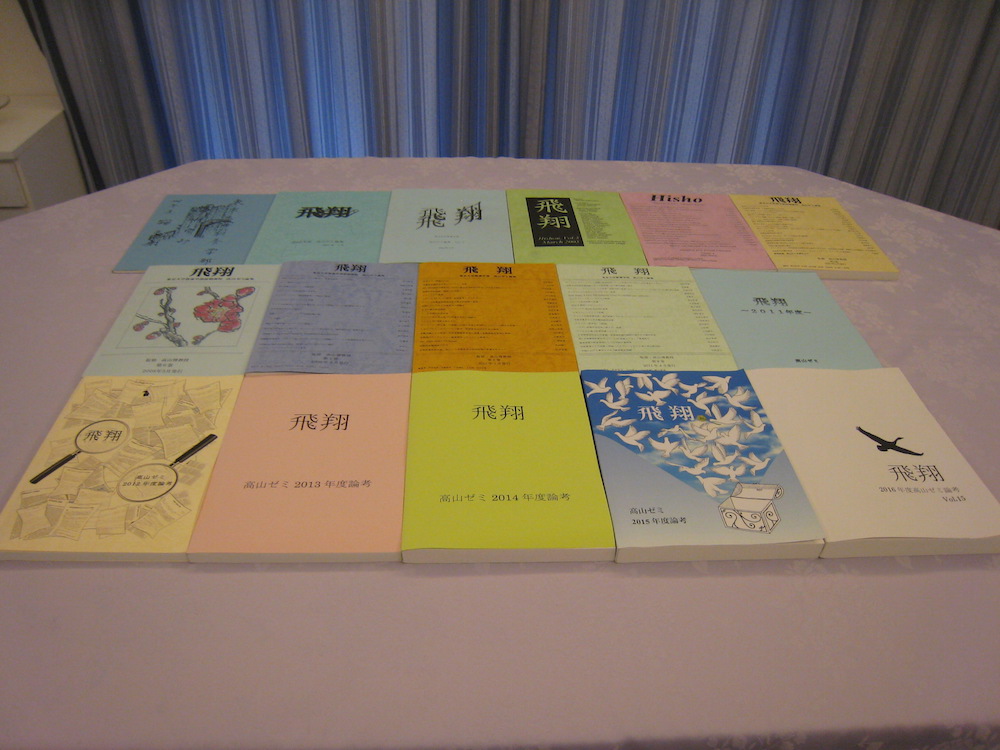今年も大学入試センター試験まで残すところ約1週間となりました。東大新聞では、今年も受験生に役立つ情報をお届けする「受験生応援連載」を通じて、東大を目指す受験生を応援します。今回は、現役東大生がセンター試験直前の過ごし方で意識していたことや、勉強の工夫をアドバイスします!
◇
センター直前の過ごし方
「夜型の生活を改め、試験開始時間に合わせた朝型の生活を送っていました。自分の場合は朝食を食べると眠くなるので量を抑え、代わりに眠気覚ましの濃いコーヒーを飲みました。勉強の合間には、受験生の友人とLINEをして励まし合いました。これは結果的に緊張を和らげる効果があったと思います」(文Ⅲ・2年)
「絶対に風邪をひかないように、できる限り家にこもり常に加湿器を付け、早寝を徹底しました。少しでも考えが煮詰まったときは、家族とおしゃべりをしたり、明るくテンポの良い音楽を聞いて気分転換しました」(文Ⅲ・1年)
「センター1週間前からは、自習時間確保とインフルエンザ等の感染症に罹患しないように学校の授業を休みました。睡眠時間を8時間確保し、毎日R1ヨーグルトを飲みました。気分転換には外を散歩し、当時流行していた恋ダンスを練習してリラックス。勉強を頑張り過ぎず体と脳のコンディションを第一に考えていました」(文Ⅱ・2年)
「センター試験本番で力を出し切れるように、年が明けてからはそれまで夜型だった生活を朝型に変えました」(文Ⅲ・2年)
「センター試験直前だからと言って特に意識はせず、今までと同じ時間の使い方をしていました。風邪をひかないようにマスクは着用していました」(文Ⅲ・1年)
「生活リズムを正すことを意識していました。夜更かしはせずに朝から勉強を始め、実際の試験時刻には頭が働くようにしました。また、東大受験においてセンター試験は単なる通過点だと考え、成功しても失敗してもどちらでも良いと割り切っていました。『私大センター利用チャレンジゲーム』のようなノリで臨むのが良いと思います」(法・3年)
「センター直前は、風邪をひかないように体調管理をいつも以上に心掛けていました。それから、2次試験前もそうだったのですがいつもチョコレートを持ち歩いていました。何か好きなお菓子があるのなら試験の時にも持って行くことをお勧めします」(文Ⅲ・1年)
「生活面では特にそれまでと変わったところはありませんでした。ただ、気持ちの持ち方として、間違えた問題があってもネガティブに考えるのを避け、『本番ではきっと上手く行くだろう』とポジティブに考えながら勉強するようにしていました」(文Ⅲ・2年)
「普段と変わらずリラックスして過ごしていた。風邪、インフルエンザ、疲労等の予防のためになるべく家から出なかった」(文Ⅲ・1年)
直前期は本番を最高のコンディションで迎えるため体調管理を徹底し、精神面でもポジティブな気持ちを意識的に持ち続けることを重視する意見が多いようですね。
センター直前の勉強の工夫
「とにかく数学が苦手で、そこで失点したくなかったので、センター数学専用の参考書に取り組みました。本番前々日には大手予備校の予想問題を、前日には前年度の過去問を、それぞれ全科目解きました」(文Ⅲ・2年)
「駿台の青パックやZ会の緑パック(予想問題集)を、実際の試験の時間帯で解いて当日の感覚を掴むことを意識しました。英語は、英単語のアクセントと発音を直前まで確認していました。数学は勘が鈍らないように1Aまたは2Bいずれかのセンター模試を1日一つ時間を計って解いていました」(文Ⅲ・1年)
「数学のセンター試験独特の誘導を苦手としていたので、慣れるため何度も過去問やセンター型模試を用いて演習しました」(法・3年)
「ひたすらセンター本番を想定して過去問やセンターパックを解いていました。臨場感を出すためにも、YouTube上にある試験中の雑音を流しながら解きました。間違えた問題も参考書等を使ってしっかりおさらいし、穴がないようにしました」(文Ⅱ・2年)
「基礎の再確認を徹底し、センターで取りこぼさないことはもちろん、2次でも生かされるような勉強をしようと考えていました。例えば数学では、2次でも頻繁に出題される確率漸化式や微分・積分の基本問題を解いていました」(文Ⅲ・2年)
「過去問や学校で配られた予想問題をひたすら解いていました。間違えた問題はどこを間違えたのかをノートに書いたりしていました。地歴等の4択の問題は一つの選択肢に対してどこが誤っているのかを説明できるくらいになるまでやっていました」(文Ⅲ・1年)
「疲れがたまり点数が悪いと落ち込むと思ったので、5教科セットで解くのは年末くらいまでにしました。代わりに各教科について、一度解いた問題を5分から10分短い制限時間で解く練習を重ねました。練習で短い設定時間に慣れておけば、本番で余裕が持てるはずです。間違えた問題は、『解説を読んで解ければ良い』と開き直ることを意識しました。自分の実力で取れる問題を落とさないことの方が大事だと思います」(法・3年)
「各教科それなりに時間を割いたのですが、特に苦手だった数学、年明けから対策を始めた生物基礎に費やした時間が多かったです。国語、特に現代文は直前にどうにかなるものでもないと思ったので年明けからはほとんど手を付けませんでした」(文Ⅲ・1年)
「数学が大の苦手だったので勉強時間の大半をセンター数学の過去問に費やしました。60分では到底終わらず、悩んでいる時間がもったいないので、詰まったらすぐに見切りを付け別の問題に移ろうと心掛けました。時間感覚を身につけようと思ってある年度の過去問を一度すべて解いて、その直後に同じ問題を今度は時間内に解き切ってみるという練習もしました」(文Ⅲ・1年)
「センター直前は数学の基本的な考え方をずっとさらっていました。理科基礎も直前に詰め込んでいました」(文Ⅰ・1年)
「全範囲を広く浅く復習するようにしていました。深い知識を集めようとすると知らないことがたくさん出てきて焦ってしまいそうだったので、深入りは避けていました。特に直前は、教科書を見た分点数に直結しやすい社会科を詰めていました」(文Ⅲ・2年)
「過去問をひたすら解いた。時間が足りなくなりがちな英数国は時間を計って、足りなくならない理社は計らずにやった」(文Ⅲ・1年)
直前期は過去問等を使って本番を想定した練習を積みながら、自分の課題意識に応じて最後の追い込みをかけていたようですね。
◇
いかがでしたか?ご自分にとって納得できるものがあれば是非参考にしてください!
【受験生応援2019】
入試担当理事が語る、東大の求める学生とは