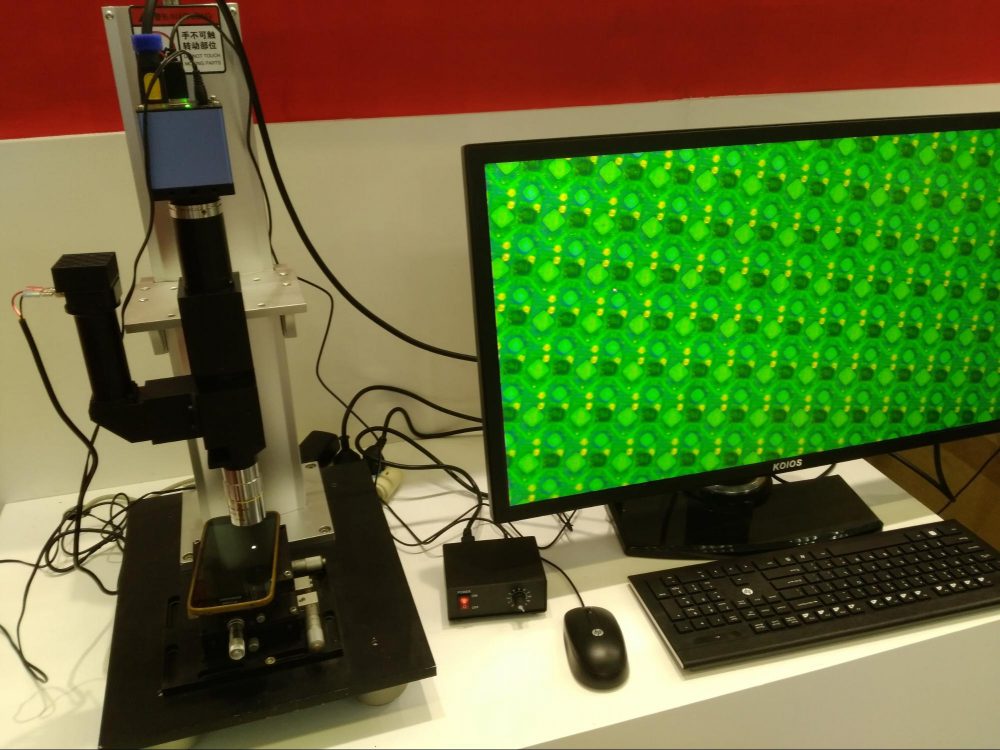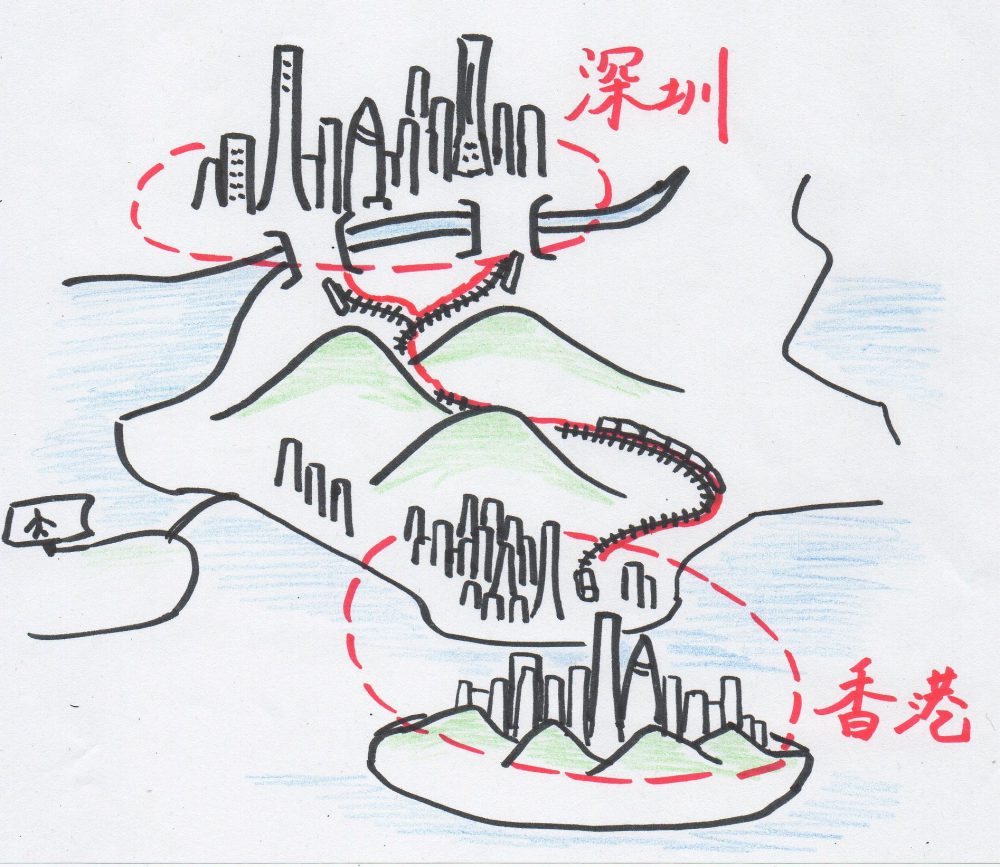平成31年初場所をもっての引退を表明した横綱・稀勢の里。本場所開始時点で唯一の日本人横綱として大きな期待を受けながら、残念な結果に終わることとなった。そこで、フジテレビ系列「さんまの東大方程式」出演時に稀勢の里への愛を語るほどの大ファンである新井謙士朗さん(法・3年)に、その思いを寄稿してもらった。
旅行先で偶然発見した稀勢の里関の手形写真。
平成25年5月場所14日目結び前の一番、土俵の上には2人の力士が立っていた。
かたや、白鵬。言わずと知れた角界の第一人者だ。前場所を全勝優勝で飾った彼はこの時ちょうど43連勝の真っただ中だった。土俵の上の白鵬は何か悠然たる雰囲気を漂わせていて、勝って当たり前、負けるわきゃない、そんな調子である。
この男に立ち向かうのは、大関・稀勢の里。はじめて聞いた名前だ。なんだか堂々とした雰囲気はある。こりゃ期待できるかもしれないな、久しぶりに日本人で優勝するかもしれないとかいうので騒いでいるのはこの人か。
私はそもそも、相撲を熱心に見ていたような人間ではなかった。世間が少し騒いでいるから興味本位でちょっと見てみるか、とNHKにチャンネルを合わせて夕方になぜか少しドキドキしながらテレビの枠越しに相撲を眺めただけなのである。
にわかに盛り上がって土俵上がアップになる。取組がはじまるらしい。両雄がにらみあう。刹那、龍虎の激突。満場の歓声が大鉄傘をゆるがさんとする。がんばれがんばれ、なんだなんだ、勝つのか、どうなんだ、がんばれ、いけっ、おおっ、ああっ。あーっ。
昨日まで名前も知らなかったこの日本人力士は長い相撲とはなったが結局はあっけなく土俵に散った。まあ、そんなものか、そう思ったが、なぜかこの少しふてぶてしい顔をした力士に興味を持ってしまった。この人はなんで騒がれるんだろう。幸い、今の世の中にはインターネットという便利なモノがある。ちょっと検索してみると、稀勢の里には熱狂的なファンが大量にいることが分かった。別に、熱狂的なファンが多いと書かれていたわけではない。表示されるツイートを見れば明らかだ。Twitter上で稀勢の里はネタにされ続けていた。どうやらここ一番には強い人ではないらしい。いや、ここ一番で勝つときも多い。しかし、勝つときはいつもその前に取りこぼしをしている。だから、手に負えない。弱くはない。でも、ここ一番で負ける。もう期待しない、と思うと、目を見張るような番狂わせをする。だから、また戻ってきてしまう。
土俵上の様子も特徴的だ。そんなこともネタにされていた。でも、どれも嫌味な感じはしなかった。この人は愛されているんだな、そう思った。
それだけじゃない、稀勢の里は中卒叩き上げの力士で、出世も速く、10年前から将来を期待され続けてきた人なのだった。なんせ、貴乃花、北の湖、白鵬と並び称される出世の速さ、幕下にいて「萩原」といっていた頃から応援するオールドファンも多くいる、有名力士のひとりだった。
それから、稀勢の里を追いはじめ、いつしか、相撲そのものにも興味を持つようになった。
しまいには、国会図書館に相撲雑誌を閲覧しに行くようにまでなってしまった。
***
平成25年、稀勢の里は好調だった。5月以降どの場所でも11勝か13勝は挙げた。稀勢の里を横綱に、そんな声もちらほら出てきた。
横綱の昇進条件、それは「二場所連続優勝、もしくはそれに準ずる成績」である。
稀勢の里には優勝がなかった。次点はたくさんあった。次第に「第二の豊山」と呼ばれるようになった。豊山というのは、学生横綱出身で、十両で全勝優勝を果たし、37勝という抜群の成績で大関に昇進、スピード出世で将来を期待された人だが、優勝なしで引退した。大双葉の弟子であり、後に日本相撲協会の理事長にもなった。
豊山にも稀勢の里にも高い壁が眼前にそびえ立っていた。それは、大鵬、白鵬という類稀なる大横綱だった。白鵬という壁は、あまりにも高かった。
余談だが、昭和の横綱で二場所連続優勝で昇進した人などほとんどいない。双葉山(関脇〜横綱で5場所連続全勝優勝)、栃錦、大鵬、北の富士、琴櫻ぐらいだろう。二場所連続優勝を絶対の条件とするのは平成期の変則である。「準ずる成績」で上がった人のほうが大多数だ。北の湖、千代の富士もそうである。今の理事長は8回も優勝しているのに、連続優勝はないから、平成基準だと横綱になれなくなってしまう。
だから、稀勢の里ほど強ければ横綱になるのには遠慮は不要…のはずだが、やはりネックになったのは優勝経験がないことだ。無論、優勝なしの昇進の例はある。照国(綱をつけた姿が稀勢の里そっくり!)と双羽黒だ。だが、さすがに稀勢の里も高齢、両者と同様な理由で、「将来を期待」と上げるわけにもいかない。
だから、稀勢の里は1回でも優勝すれば昇進させていいだろう、という声が有力説となっていった。
***
ところが、そのあと起きたことといったら悔しい事態ばかりだった。
まず、平成26年初場所、稀勢の里は足の親指を負傷し、大関になってから初の負け越しを、初土俵以来初の休場をすることで記録することになってしまった。稀勢の里の強さはよきにつけ悪しきにつけなんだかんだ言って安定していること、鉄人と称された人であっただけに休場は、衝撃だった。
そこからの2年間は忍従の日々(昭和56年の大河ドラマ『徳川家康』より。師匠・隆の里は、糖尿病との長い闘いの末に横綱の座を摑み、「おしん、家康、隆の里」と言われた)だった。平成25年の安定感はどこへやら、10勝近辺をうろうろする場所が続き(それでも大関としては強いのだが)、横綱という声もかき消された。
そんなこんなしているうちに、大関・琴奨菊が平成28年の初場所に優勝した。
琴奨菊の初優勝は素直にうれしい。
だが、テレビで報道を見るほうとしては、悔しさしかない。テレビ報道は琴奨菊一色である。つい先日まで稀勢の里と言っていた人たちが今度は手のひらを返して初優勝を果たした大関を褒めそやすのだ。なんだ、みんな、稀勢の里、稀勢の里と言ってたくせに、琴奨菊が優勝したら、そっちに乗り換えるのか、稀勢の里の優勝を待ってたんじゃなかったのか。何が日本出身力士の10年ぶりの優勝だ、そんなものはどうでもいい、稀勢の里の優勝が見たいんだ!と。
そのうち、遅れに遅れて大関に上がった豪栄道までもが優勝を、しかも全勝で達成するに至り、どうして地力ではあきらかに上の稀勢の里が優勝を逃し続け、他の角番多数の大関が(ごひいきの方には失礼!)ワン・チャンスをつかんで優勝するのだろうか?という疑問ばかりが頭を駆け巡った。稀勢ファンの悩みはおそらく本人よりも深く、重かっただろう。
「本人より」と言ったのは、別に本人が悩んでいないという意味ではないのである。稀勢の里はメンタルが弱いと言われた。だが、大関まで昇った人がメンタルの弱いわけがない。むしろ、ここまで跳ね返され続けても諦めない強い心の持ち主だ。弱いのはファンのメンタルだ。辛抱たまらず、「豆腐メンタル」と言ってしまう、そんな我々自身の弱さだ。
***
そんな稀勢の里に、初優勝のその日は意外にあっけなくやって来た。
平成28年、稀勢の里は初場所こそ振るわず9勝6敗で終えたものの、以降は調子を取り戻し、平成25年以来の強い稀勢の里が戻ってきた。
稀勢の里には「1回」が遠かった。だから、ファンの間では、きっと、最初の1回、優勝できてしまえば、あとはスルスルと優勝できるようになる、そんな予測すらあった。
平成28年の後半は毎場所のごとく話題は綱とりだった。思えば、このころが力士・稀勢の里の最強時代だった。そしてそれに立ち会えた我々は幸せな人間だったのだ。こんなところも師匠・隆の里に似ていた。隆の里は、1年間だけ最強と言われた。稀勢の里も、1年間だけは最強の力士だったと思う。
運命の平成29年、初場所、その日はやってきた。しかも、思ってもみないかたちで。
稀勢の里はこの場所、琴奨菊に敗れただけの1敗で好調、最大のライバル・白鵬は平成28年以来不調で、稀勢の里は優勝争いの単独トップに立った。
…とここまでならよくある話だ。
前述の通り、こんな状況で稀勢の里はことごとく負け続けてきた。稀勢の里は無茶苦茶に強い力士だ。なのに負けている記憶しかないのは、ここ一番にすべて敗れてきたからだ。なのに、応援してしまうのは、目を離そうとすると、突然輝きを放ちだすからだ。
しかし。14日目、逸ノ城戦。大多数のファンがあるいは負けるだろうと思っていたのに、稀勢の里は勝った。
そして結びの一番。なんと白鵬が貴ノ岩に敗れた。こういう時には絶対に負けない人なのに。そして。
この瞬間。
待ちに待った稀勢の里の幕内最高優勝は達成されたのだ。
感動もひとしおだ。
千秋楽。対戦するは横綱・白鵬。
やっぱり負けるんではないのか。そんなふうにも思われた。もう優勝も決まっているんだし。
しかし。
稀勢の里は勝利をその手に摑んだ。
白鵬は全力で向かってきてくれた。
「横綱への試験」、と評された、そんな見事な相撲を見せてくれた。
そして、稀勢の里は全国民の祝福の中で横綱昇進を決めた。
***
ようやく稀勢の里が横綱となり、喜びいさんで奉納土俵入りを見に行った。
白妙の 富士の高嶺に 降り積もる 雪のごとくに かがやける綱
遠目からしか見られなかったけど、稀勢の里は輝いていた。横綱らしい堂々とした姿で、もう何年も横綱だった人のようだった。
***
稀勢の里は、強い。
なんてったって「史上最強大関(優勝制度確立以降)」だ。白鵬にだってよく勝つ。63連勝も43連勝も真っ向から止めた。強い時にはだれにも負けない。初顔にだって強かった。それに、勝った時の傲然として自信に満ちあふれた姿、強豪中の強豪を見ているような気になる。北の湖のようだともよく言われた。
稀勢の里は、美しい。
常に真っ向勝負をつらぬき、立合いにかけひきをしない。そんな相撲の取り口、身長188cm(大正期の大横綱、太刀山と同じ!)、体重177kg、見事な太鼓腹、そんないかにも力士らしい姿、そして勝っておごらず、負けて腐らない、黙して語らない態度。負けても言い訳しない。負けて涙したことはない。人の前では。相撲的な「美」を表したような、そんな人だった。
稀勢の里は、かわいい。
「萩原」といっていた頃は子どもを見るようなかわいらしさだが、大関になってからも、土俵上でまばたきする姿、顔つき、これより三役のときのいわゆる「スタスタ」などは(稀勢の里は千秋楽のこれより三役のときに1人だけ早く出ていってしまう。これがTwitter上などで「スタスタ」と呼ばれた)稀勢の里のかわいらしさだ。
稀勢の里は、かっこいい。
切れ長の目、高身長、寡黙な態度、どれを見ても男前だ。ファンの中には、「腰高」との批判に、「スタイルがいい」と言い換えて対抗した人もいた。
そして、稀勢の里は、魅力的だった。
だから、稀勢の里は愛された。
***
そう、稀勢の里ほど愛された力士はいなかった。それは稀勢の里が発する魅力によるものだ。
稀勢の里ほど愚直な男はいなかった。絶対に逃げない、そう言った男は、本当に逃げることなどしなかった。
古風な力士だった。お相撲さんの鑑のような人だった。テレビにも出なかったし、黙して語らなかった。土俵態度も誠実だと思う。
稀勢の里に人生を見る人さえいた。生き様は、だれよりも愚直で、それゆえにだれよりも破天荒だった。こんな生き方はだれにもできない。
だれよりもたたかれた。だれよりも愛された。
しかし、何も言わなかった。そんなところがより人の心をつかんだ。稀勢の里には中毒性がある。一度見たら、もう離れられない。そんな感じが。放っておけないのだ。優勝だけはしないのに、大金星ならいくつも挙げてしまう、そんな稀勢の里は。
双葉山の連勝を更新できるとしたら、稀勢の里しかいないと思った。双葉山という人は若い頃、決して番狂わせを起こさない人として知られた。たまには変化でもして観客をあっと言わせりゃいいのに、そんな陰口もたたかれた。しかし、双葉山は何を言われようと真っ向勝負を挑み続け、負け続けた。しかし、双葉山は、ある日突然、負けを忘れた。そしてそのまま前人未到の5場所連続全勝優勝、偉大なる69連勝を達成し、大横綱となられた。双葉山は一度勝った相手には二度と負けなかった。徐々に地力を上げ、一度勝てば確実に勝ち、地力が全員を上回ったときにはもうだれにも負けなくなった。稀勢の里も、勝ち数を少しずつ増やし、地道に安定する勝ち星数をゆっくりと増やしていった。9勝から10勝、11勝、13勝。最後には15戦全勝で安定する。そんな期待を抱かせるほど、稀勢の里は魅力的だった。
***
平成28年春、大阪場所。日本中が歓声に包まれた、あの優勝。と、その後の休場の続く横綱在位期間。
晩年はもう諦めかけていた。あとは引退がいつなのか、それだけだと思ってもいた。仕方がない。
だけど、もしかしたら、とも思った。だって、稀勢の里は、人にはできないことをあんなにやって見せた人だから。あんなにいっぱいの奇跡を見せてくれた人だから。
でも。
今回ばかりは、そうはいかなかった。
平成の終わり、第72代横綱・稀勢の里は、土俵を去る決断をした。
みをつくし 綱張りさかづき たまはりし なにはのことも 夢のまた夢
***
思えば、相撲を見はじめたのも、双葉山の相撲道を知ったのも、全部稀勢の里のおかげだった。そう、稀勢の里こそ、相撲のすべてだった。
稀勢の里時代は、確かにあったのだ。たった1年だったけれど。夢は現実になっていたのだ。「稀な勢い」は本当にあったのだ。それは驚異的なスピードとかじゃない、じょじょに、ゆっくりとではあるが、確実に地力を高めて最強の力士の座に到達するという史上にも稀な進み方を表現していたのだ。
稀勢の里と同じ時代を生きられてよかった。
ありがとう、稀勢の里。夢を、希望を、そして強さを。
(文中敬称略)
寄稿=新井謙士朗
新井謙士朗(あらい・けんしろう)